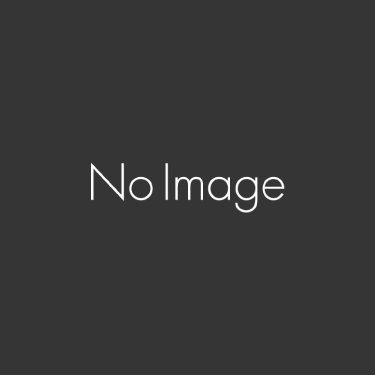決算の季節が近まって参りましたので、毎年決算資料とのにらめっこをしています。
本記事では、五島市の生活保護の実数を紹介し、その背景にある経済構造について考察します。
① 概況:被保護世帯・人数・保護率の推移
| 年度 | 世帯数 | 人員 | 保護率(%) |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 641 | 792 | 2.29 |
| 令和3年度 | 646 | 796 | 2.35 |
| 令和4年度 | 653 | 803 | 2.42 |
| 令和5年度 | 640 | 782 | 2.40 |
| 令和6年度 | 610 | 727 | 2.28 |
分析:
世帯数・人員ともに令和4年度をピークに減少傾向。
令和6年度には世帯数・人員ともに令和2年度を下回っている。
ただし保護率(2.28%)は全国平均(1.62%)・長崎県平均(2.00%)を上回る状態を維持。
考察:
五島市の生活保護率は依然として高水準であり、地域の経済的脆弱性が継続しているとみられます。減少傾向は「廃止世帯数>新規開始世帯数」であることを示し、医療扶助費抑制や高齢者死亡による減少の影響が考えられます。
② 世帯類型別構成(ハンディキャップ層の内訳)
| 年度 | 高齢者世帯 | 障害者世帯 | 傷病者世帯 | 母子世帯 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 398 (62.1%) | 84 (13.1%) | 86 (13.4%) | 22 (3.4%) | 51 (8.0%) | 641 |
| 令和3年度 | 403 (62.4%) | 87 (13.5%) | 88 (13.6%) | 19 (2.9%) | 49 (7.6%) | 646 |
| 令和4年度 | 404 (61.9%) | 89 (13.6%) | 94 (14.4%) | 18 (2.7%) | 48 (7.4%) | 653 |
| 令和5年度 | 397 (62.0%) | 85 (13.3%) | 91 (14.2%) | 18 (2.8%) | 49 (7.7%) | 640 |
| 令和6年度 | 385 (63.1%) | 81 (13.3%) | 86 (14.1%) | 19 (3.1%) | 39 (6.4%) | 610 |
分析:
「高齢者世帯」が約6割超で、圧倒的多数を占める。
「障害者」「傷病者」も合わせて約3割近くを占める。
「母子世帯」「その他」は少数。
高齢者構成比は令和2年度の62.1%→令和6年度63.1%と上昇傾向。
考察:
五島市の生活保護は「高齢・疾病・障害」要因による受給が大半。離島特有の就労機会の少なさ、交通制約、医療アクセスなどが構造的要因となっており、今後も高齢化進行に伴いこの構成が固定化する懸念があります。
③ 地域特性と課題
1. 地理的ハンディキャップ
離島という地理的条件から、雇用機会の少なさ・交通費負担・医療機関の偏在が継続的な課題。
働ける世代でも障害・疾病・高齢を抱えるケースが多く、自立支援策が届きにくい構造。
2. 高齢化の進行
全国平均(高齢者世帯54.8%)、長崎県平均(58.3%)を大きく上回る構成比。
今後の高齢単身世帯増加により、医療・介護扶助費の増大リスクが継続。
3. 医療扶助費の負担
被保護世帯人員の減少により医療・生活扶助費全体は抑制傾向。
生活保護件数の内訳
| 区分 | 世帯数 | 人員 |
|---|---|---|
| 保護申請 | 68 | ― |
| 保護取下 | 4 | ― |
| 保護却下 | 5 | ― |
| 保護開始 | 59 | 67 |
| 保護廃止 | 99 | 108 |
分析:
開始より廃止が多く、純減(世帯ベースで▲40)。
生活保護制度が「新規流入よりも自然減(死亡・高齢者世帯の終結)が上回る」段階にある。
保護開始の理由分析
| 主な理由 | 世帯数 | 構成比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 世帯主の傷病 | 20 | 33.9% | 病気・けが・慢性疾患など健康要因が最多 |
| 預貯金の減少・喪失 | 21 | 35.6% | 預金取り崩し後の生活困窮、資産要件該当 |
| 定年・自己都合による失業 | 3 | 5.1% | 高齢者の退職後無収入化 |
| 老齢による収入減少 | 1 | 1.7% | 年金額不足層 |
| 社会保障給付金の減少・喪失 | 1 | 1.7% | 年金・手当打切り |
| 仕送り減少 | 6 | 10.2% | 離島特有の都市部家族からの支援減 |
| その他 | 4 | 6.8% | ケース移管など含む |
傾向まとめ:
**「病気」と「預貯金の減少」**が合わせて約7割を占める。
高齢者・単身高齢世帯が「病気+資産枯渇」で申請に至る構図。
「失業」「事業不振」など労働市場要因は少数で、経済的ショックよりも長期的な生活困難が中心。
保護廃止の理由分析
| 主な理由 | 世帯数 | 構成比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡 | 35 | 35.4% | 高齢単身世帯中心 |
| 働きによる収入増加・取得 | 14 | 14.1% | 就労・収入改善 |
| 社会保障給付の増加 | 4 | 4.0% | 年金等の支給開始など |
| 親族縁者の引取り | 3 | 3.0% | 同居再編による脱却 |
| 施設入所 | 5 | 5.1% | 高齢・障害施設への移行 |
| その他 | 35 | 35.4% | 自然廃止、長期入院、転出など |
傾向まとめ:
廃止理由の最多は**「死亡」および「その他(自然減)」で全体の7割**。
「働いて脱却」は14世帯(約14%)にとどまり、自立支援型の廃止は限定的。
「施設入所」や「引取り」など、高齢者福祉制度・家族支援による移行が見られる。
開始・廃止の構造比較
| 観点 | 開始 | 廃止 |
|---|---|---|
| 主因 | 傷病・資産喪失 | 死亡・自然減 |
| 主層 | 高齢・病弱 | 高齢単身者 |
| 性質 | 生活困窮の新規流入 | 高齢化による自然退出 |
| 政策的示唆 | 健康・医療・貯蓄支援の充実 | 終末期支援・看取り福祉の強化 |
考察:
五島市の生活保護は、労働市場よりも生命・健康・老後に起因する福祉型保護。
「開始は病気・資産喪失、廃止は死亡」という循環構造を示しており、
保護が一時的救済ではなく、生涯支援型(終生利用型)に傾いていることがわかります。
筆者の実感
兼ねてから五島市は「賃金の低さ」が指摘される事が多いと感じていました。
それに加えて、高齢化の進展も重なり生活保護に陥るケースが増えているのが実体です。
市民の方からは、年金の受給額が少なく、生活保護の受給者に対する不満の声が少なくありません。
医療・交通・買物も含めて高齢者の生活が中々に厳しいのが五島市の現状です。
増え続ける医療費の単なる抑制ではなく、「予防的福祉(医療・生活習慣病予防)」と「地域包括ケアの充実」が重要な方向性となりそうです。