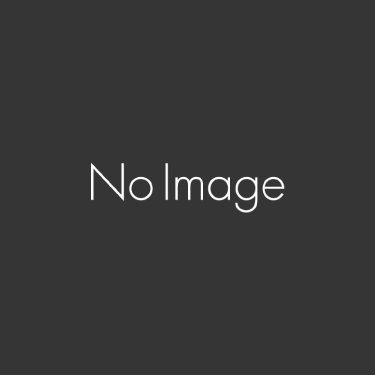(楽天)【中古】ヒトラー・ユーゲントの若者たち—愛国心の名のもとに
以下、私が本を読んでまとめた内容です。
ヒトラー台頭の背景
ベルサイユ条約によって多大なる賠償金を請求されたドイツは、国内の失業率増加に伴い、深刻な経済のダメージを受けていた。
そんな中必要とされたのは、コツコツと現実的に経済の再生を担うような指導者ではなく、現状を一変させてくれるほどの指導力と力を持った人物。
そうした、ヒトラーが独裁者になりえた背景を考えると、それが結果としてもたらした災禍に対する原因は、決して独裁者その人だけに帰属しうるものではない。
ヒトラーは単なる代弁者に過ぎなかったのではないかと。
たまたま、人心を掌握するノウハウに長けた人物が、その声に応じる形で出現しただけではないのかと。
そう考えるとむしろ真の原因は、やはりベルサイユ条約が定義した無慈悲な押し付けだったのではないだろうか。
「とうとう現れたんだわ―私は思いました―私たちをこの混沌とした世界から救い出してくれる人が」
(本文より抜粋)
多くの国民が希求していたのは、希望を与えてくれる指導力であり、その中身を吟味する前に飛びついてしまうほどに、深刻な問題を抱えていた。
教育と洗脳
子供達に与えられた洗脳の恐ろしさは、注目に値する。
「学校ではカリキュラムが変わり、新しい科目が二つ加わった。人種学と優生学であった。」
繰り返し、繰り返し、ユダヤ人に対する劣等生と、アーリア人に対する優勢性が教え込まれた。
それは批判的に物事を考えるということを知らない子供にとっては、非常に大きな、思考基盤となったはずである。
だからこそ、残虐な行為に対する免疫、認知的な正当性が担保されていたのだろう。
「しかし、ユダヤの人口は52万人。人口の1%以下に過ぎなかったのである」
この事実は私にとって少々驚きで、大体5%くらいはいるのかと思っていたが、全体に占める割合がその程度だったとは知らなかった。
このことから考えられるのは、数の理論に基づく少数派の圧倒的な弾圧だ。
反抗しようにも数が足りず、(なにしろ彼らの周りの99%は非ユダヤ人なのだから)加害者からしたら安心できる配分だったのだろう。
共通の敵を作るということは、とりわけ団結の意識を強める。
それは日本の江戸時代も同じことだったのかもしれない。
戦争の開始に伴う安楽死計画
「障がい者のための病院=無駄飯暮らし=殺してよし」
という短絡的かつ恐ろしい理論がまかり通ってしまうほどに、ヒトラーの独裁的立場は強固なものとなっていたことが伺える。
ユダヤ人を虐殺している時点で普遍的な人間の尊厳を尊重していないというのはわかるが、今度はその矛先が自国民に向けられたという点は注目に値する。
つまり、ヒトラーの政権は、生きるべきものの範囲を自らの手によって狭めている(アーリア人→戦争に加担できる人)。
戦争が深刻になるにつれて、およそ戦争に役立たない人から抹殺されるようになるというのは、もやは同朋という概念さえも通用しなくなり、完全なる無秩序である。
軍事政権の独裁は、いかなる人間的な論理をも蹂躙する。
抵抗しながら生きること
一部の勇気ある青年たちは、それが方向性として大いに誤っているのだということをはばからずに主張している。
それは後世に生きる人への大きな希望である。
ある迫害を受ける親が子供に送った言葉が感動的だ。
「私が何よりも望んでいるものは、お前たちが胸を張って、まっすぐに、自由の精神をもって生きていくことだ。たとえ、それがどんなに困難なことだとしても」
戦争の困難さ、横暴さを認めることのできる言葉の中には、
「彼らはまだどう生きるべきかは知らないうちに、どう死ぬべきかを知っていた」
という述懐がある。それは本当に、生きるということはなんなのかということを考えさせる。
教育を疑う
収容所での少年の述懐では
「自分はドイツをよりよい国にするために、自分を犠牲にし、身を粉にして働いたのだ。自分の行動は、祖国と、そこに住む人々への愛に基づいていたのだ。」
とある。ヒトラーがその感情を巧みに利用したのは事実だが、このことから学ぶべきことは別の点かもしれない。
つまり、成果を残すために頑張る気持ちは大事だけど、気持ちだけでは圧倒的に不十分であることだ。
彼等だって彼等なりに、ある水準では主体性をもって物事を判断していたのだろう。
ただ、自分たちが受けてきた教育そのものに対する懐疑まで及ぶことはなかった。
「いや、そもそもこの教育って・・・」
そうした疑いは、ある程度広い視野で考えなければ、見えてこないのかもしれない。