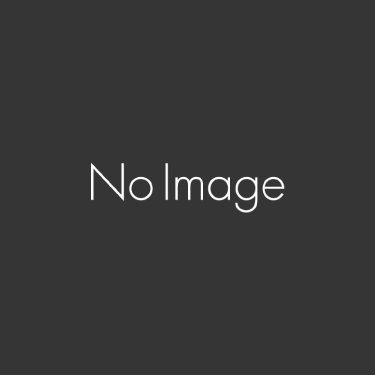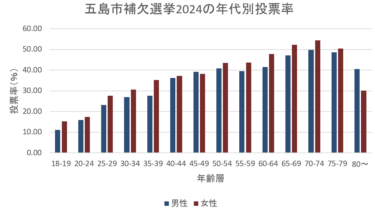移住促進に成功している自治体ってあるの?
成功すると、どんな良い事があるの?
五島市の事例を参考に、こういった疑問に答えます。
この記事を読むと、移住促進が成功した場合のメリット・デメリットが分かります。
目次
なぜ移住促進?
自治体が移住促進を進める理由は、人口減少しているからです。
人口減少には2種類あり
- 自然減:生まれる人と亡くなる人の差
- 社会減:転入する人と転出する人の差
私が移住した五島市は、「社会減」が初めて「社会増」に転じたとして、注目を浴びました。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/goto_jp_5e527c93c5b629695f5bd65d
以下、五島市の取り組みを詳しく解説し、移住促進が成功した場合のメリット・デメリットを紹介します。
五島市の最重要課題
五島市は、最重要課題として、人口減少対策に力を注いでいます。
H30.6月の議会で市長が述べた「人口減少対策5つの柱」は
国境離島新法を活用した支援事業
世界遺産登録推進事業や体験型民泊事業など観光の振興を図り、観光資源を活用した起業・創業により移住・定住
UIターン促進事業
浮体式洋上風力発電ウインドファーム事業
日本語学校の開設準備作業
です。
こうした様々な移住者支援の成果のおかげか、
UIターンを始めとする年々移住者の数は増えています(2019年は202名移住)。
しかし、人口全体で見ればマイナスの傾向(社会減+自然減)が続いているため、今後は日本国と同様、人口は減っていきます。
日本の地方はどこも「人材の奪い合い」みたいな状況になっているので、ゼロサムで全体を見れば、
五島市の人口が増える=他の自治体の人口が減る
という事を意味します。
移住促進のメリット
①経済が回る
住民目線では、人が増えると、地域に活力が維持され、学校や病院の維持が期待されます。
人口が増えるとお店や施設が増えるので、社会の中で動く血液の量が増える状態となります。
五島ではしばしば「働く場所がない」と言われます。正確に言えば、どこも人手不足なので、働く場所はあります。
賃金は増えるか?
ただ、都会のような賃金水準や労働環境を求めると、話は別です。本日も地元の高校生とお話しましたが、
卒業したら島を出たい。
という意見が殆どでした。
実際、五島では「良い職場がないから」という理由で、高校生の8割が卒業と同時に島を離れます。親御さんも、
ずっと五島にいても・・・
という方が多いです。
一方の行政サイドは、市長の号令の下、「良質な雇用の場の創出」を訴え、企業の誘致や起業の促進を行っています。
ただ、これからの時代の変化(AIの普及と終身雇用の崩壊)を考えれば、従来の1次産業・2次産業であった
「収入源が場所に限定される仕事(工場や農家など)」
の数は減少し、PCとネット環境さえあれば完結する仕事が増えていきます。
②地域に活気が出る
全国的に人手が減っているため、お祭りをするのも人手不足であり、お店も後継者不足です。
移住促進を行い、外から人を誘致する事により、地域の活力が保たれる側面もあります。
➂社会資本の維持
地域の病院・交通は人口減少に伴い規模の縮小が進んでいます。
毎年子供の数が減っているため、廃校も急増しています。
こうした社会資本を維持するためには、利用者となる地域に人が住み続ける必要があるとされています。
移住促進のデメリット
逆に、人口が増える事のデメリットです。まずは環境面から。
①環境が汚染・破壊される
かつて五島の福江島には9万人近い人が住んでいたそうですが、昔の生活と今の生活は、環境に与える負荷がけた違いに異なります。
コンビニやスーパーがすっかり普及した五島市(福江島の中心部が主)では、都会とさほど変わらない利便性があります。その分、ビニール袋やプラスチック製品も多用されるため、
市民1人が環境に与えるダメージ
は昔と比べ物になりません。当然、排出されるゴミも増えます。
おそらく、現在の便利な暮らしを続け、人口が増えた場合、新しいゴミ焼却場(この点については後日記載)の処理能力を超えてしまう気がします。
②地元からの不満
五島で生活している人からは、
移住者ばかり優遇している(; ・`д・´)
という不満の声を耳にします。
特に五島市は、住宅補助の改修や引っ越し費用の負担など、様々な面でよそから来る人を優遇しています。
そして中には、「補助金だけ貰ってサヨウナラ」してしまう人もいます。
一生懸命働いている地元の人からすると、これではあまりに不公平です。
こうした移住促進を進めていくと、かえって地元との分断が生まれる火種にもなります。
➂住環境の低下
人口が増えた場合、住民目線で考えると
- 交通量が多くなり、道路渋滞、交通事故が発生する
- 人が多くなり、犯罪や事件の確率が増える
という面もあります。実際、五島の市街地より外側に住む人の話を伺っていると、
静かな場所だから気に入っている
という声を多く耳にします。そういう感じで
「自然と共に過ごす静かな暮らし」
を望む人にとっては、人口が増えてやかましくなることは、望ましくないとも考えられます。
私の出身地である千葉県船橋市も、最近はマンションが増えすぎているため、車を運転したいとは思えません。
さらに、仕事でインドに行った時や、旅行でスリランカに行ったときは、
人口が増えすぎると、基本的にロクな事がない
と思いました。海外に行くとよく分かるのですが、
- 車のクラクションがやたらとうるさい
- スリや泥棒に合う危険性が高い
- 自然と触れ合う機会が乏しい
という部分が多いです。
メリット・デメリットのまとめ
最後まで記事を読んで頂きありがとうございます。
全国と比較しても人口減少率の著しい五島市の場合、
「人口減少対策」が市政の最大のテーマです。
移住促進により、地域に人口が増えるメリットとして、
- 経済の活性化
- 税収が増える
- 社会資本が維持される
が挙げられる一方で、デメリットとしては
- 自然環境や景観の悪化
- 地元からの不満の増加
- 住環境の低下
という部分が挙げられます。
市民の反応は?
五島市では、2020年に市長選挙があり
移住者獲得を最優先する市政 VS もっと「地元の人」を大事にする市政
が争われました。結果的に、大差で
移住者獲得を最優先課題とする市政 が選ばれました。
こうした事から、市民の大多数(有権者の半分近く)が
人口減少対策をどうにかしてほしいと願っている状況が伺えます。