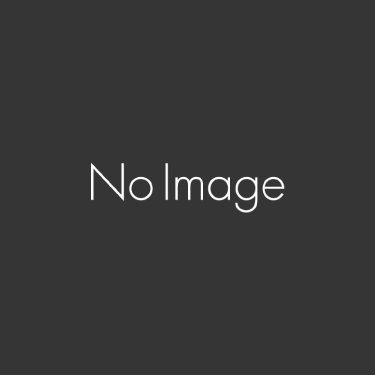映画「生きる」
黒沢明監督の映画、「生きる」を鑑賞しました。感想をご紹介します。
67年前の映画とは思えないくらいの「既視感」がありました。
https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B00VSFKB5A
※以下、内容のネタバレを含みます
ざっくりストーリーを紹介すると、
- 公務員で30年間務めた主人公(渡辺さん)が余命わずかの癌だと知る
- 渡辺さんは役所でただ判子を押すだけの人生は無駄であったと悟る
- 渡辺さんは「残りの人生」を謳歌するために街に出かけるが、ちょっと違う感じ
- 元同僚の女性から刺激を受け、渡辺さんは「市民から陳情のあった公園作り」に奔走
- 数か月後、公園の完成を間近に渡辺さんが死亡
というストーリーです。
面白いのは、主人公の渡辺さんが亡くなった後も、1時間以上作品が続くことです。
役所の縦割り構造
作品の中では、「日本の役所の縦割り組織」に対する痛烈な皮肉が盛り込まれています。
- 〇〇の件は水道課へ
- ××の件は道路課へ
- △の件は衛生課へ
というように、行政組織の硬直性が映し出されています。
そうした中で渡辺さんは、「縦割り行政」という壁に立ち向かいながら奔走し、公園の建設に尽力します。
ところが周囲の役所の人間は、「決められたことを決められたとおりにこなす」のが仕事なので、その熱意が理解できません。
中でも印象的だったのは、
俺だって若い時は(やる気に満ち溢れていたのに)・・・
言うな!(市役所は)「何もしちゃいけない仕事」なんだから・・・
と職員が本音を述べていたシーンです。
- ただロボットのように、決められたことを決められたとおりにこなす
- 誰も主体的な意思決定が出来ないシステムになっている
作品の中では、それが強く映し出されています。
恐らく監督は、「その硬直的なシステム」の中で、
今後長い間、日本人が仕事に追われ続けなければいけないことに、警鐘を鳴らしていたのだと思います。
1952年の作品だと知って驚いたのは、それが高度経済成長期、ひいては平成の時代にも通じる部分が多かったからです。
人生の時間
渡辺さんのお通夜の中で、
どうして渡辺さんは、急に人が変わったように情熱的になったのだろうか?
と市役所の職員が談義を始めます。
今までの渡辺さんは、ミイラのように判子を押すだけの仕事だったのに。。。
そこで仮説として、「渡辺さんは自分の余命が残り少ないことを知っていた」という考えが述べられます。
皮肉なのは、その中で市役所の職員の一人が、
俺だって(死ぬと分かっていれば)、主人公のように主体的・精力的に仕事ができるのに・・・
と言っていた部分です。
本当はいつ死ぬかなんて、分からないんですけどね。
死を目前にして
スティーブジョブズも言っていましたが、リアルに死ぬことが間近に迫ると、「すべては二の次」に感じるそうです。
渡辺さんも、自身が胃の癌であると知って、文字通り「なりふり構わず突き進む」覚悟を手に入れます。
そしてお通夜に居合わせた役所のメンバーは、一応飲みの席では
明日から俺たちも、渡辺さんのように、奮闘しよう!!!
という前向きな雰囲気になります。
ところが次の日、新しい課長の仕事は
かつての渡辺さんが30年間続けいた、判子を押すだけの仕事
に戻ってしまいます。
そしてその描写(市役所が縦割りのロボット仕事に戻る)が、この物語の結末です。
昨日あれだけみんなで言ってたことなのに・・・
という部分で、超皮肉です。
縦割り社会と人間の横着
人間は、組織に染まってしまった方が楽です。
決められたとおりに決められたことだけしていれば、何も考えなくて良いからです。
それはある意味で、心地よかったりもします。
ドイツのアウシュビッツも、久賀島の牢屋の窄も、加害者は
「ただ決められた通りに作業をこなしていた」
だけだったのでしょう。
黒澤明監督がこの作品の中で伝えたかったのは、
人生を無駄にしてしまう「硬直的な組織」も、本気の覚悟があれば変える事は出来る
というポジティブな面と、
人間は「差し迫った死」に直面しない限り、結局は今まで通りのやり方に甘んじて、周りに流されてしまう
というネガティブな部分だと感じました。
公開から67年の歳月を経てもなお、
その本質が色あせないという面で、素晴らしい映画作品です。