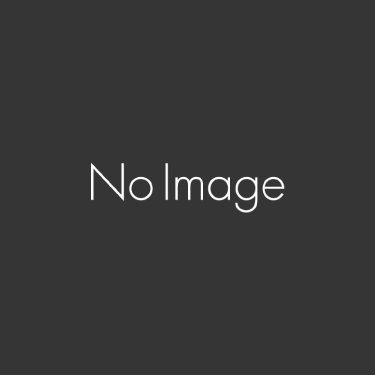五島市の市議会では、議事録が閲覧可能になるまでに、数か月かかります。
そこで、議事メモを残しています。
※内容は正式な議事録ではないため、発話の全てを反映しておらず、必ずしも正確でない箇所もあります。
日時 2025/9/18 13:15ー
目次
南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されたことについて
指定に係る経緯と意義について
田口 暑い日が続いているが数ヶ月暑いと言わない日はなかった。暑いですねが挨拶となった。暦の上では秋。彼岸の入りですが、暑さはまだまだ続くようですのでご自愛ください。南海トラフ防災地域に指定されたことについて。全国の指定市町村は723となった。指定基準は津波の高さが3m以上で堤防が低い地域になっている。富江港の一部が指定されたと報告があった。振動を感じる揺れは経験がなくピンとこないが、前市民が防災対策に取り組むことが大切。指定の経緯と意義は。
市長 7月1日、国が被害想定に基づき基本計画を改定し県内の7市1町を指定。今年5月に国から県を通じて意見を求められて意見なしと回答している。地震や津波の経験がなく自分ごととして捉えられないのが現状と思う。改めて市としての体制を整備するだけでなく啓発活動を行い防災意識を高めたい。
田口 不特定多数の人が出入りする機関にも計画作成が求められる。防災対策計画の主な内容や考え方は。
総務企画部長 南海トラフ地震の指定を受けて津波からの防護・迅速な救助・連携を定めた防災対策推進計画を策定する必要がある。30cm以上の浸水区域の病院やスーパーは防災対策計画策定が必要。県が説明会を開催して依頼する。
田口 指定の発端となった改修工事を一番にすると思うが施設については迅速な対応に努めるようにお願いする。
防災対策計画の内容について
田口 8月10日に玉之浦岐宿線で落石があり全面通行止めとした。玉之浦以外では放送がなかった。落石が発生したのはお盆前で、この道を通る人が多数いた。知らずに通行止めを知るのは時間計画が狂う。墓参りを断念して帰った帰省客もいると聞く。他の地区からの市民にも影響が出た。どういう理由で放送しなかったのか。何のために防災無線があるのかという声を聞いた。
総務企画部長 原則防災情報と行政情報をお知らせする。放送事故は大規模災害の避難指示・気象のほか、火災予防・振り込め詐欺の注意喚起など緊急性を考慮して放送している。五島市内の全域にするか、地区別に判断するかをしている。
田口 今後の活用について何かありましたら。
総務企画部長 今回の県道の通行止めはこれまでも経緯していなかった経緯もあり防災無線の放送はしていなかった。主要な幹線道路であり影響が大きいことから放送した。音声放送は玉之浦だけであり、誤解を生じさせる恐れがあることから、インフォカナルで情報発信している。運用規定に基づき緊急性を考慮して活用に努める。防災情報は市のHPやインフォカナルで届けたい。スマホにインフォカナルを導入するようにお願いしたい。
田口 災害に関するあらゆる情報を伝えて市民の財産を守ることが大切と思う。交通情報も含まれると思うので放送していただきたい。お年寄りは正直見ません。音声発信をお願いしたい。せっかくの放送が聞き取りにくい地域があると聞く。改善をしてもらいたい。
防災無線による放送について
防災無線の使用基準と放送範囲について
今後の活用方法について
避難施設の整備について
指定避難所について
総務企画部長 指定緊急避難場所を44箇所設置。37箇所が指定緊急避難所。屋内の指定緊急避難場所の人数は4000人ほど。
田口 経営指針について、政府は避難所の指標に国際基準を取り入れた。最低3.5平米、50人に1機のトイレが明記されている。共同通信の結果が掲載されて五島市はトイレは基準達成予定だが、時期の目処は立っていない。一人当たりの面積基準は今後も困難と回答している。国際基準に達しなくても良いと感じているように思うが、順守と対策は。
総務企画部長 昨年1月の地震の際の生活環境を見て方針改定するとしている。避難所の国際基準は3.5平方メートルで満たしていない箇所もある。県は地震アセスメントを実施して最大想定避難者数に応じて県から指示があっている。現在算出や収容人数の見直しが求められているので課題を整理して今後の対策を考えたい。
指定避難所としての公共施設利用について
総務企画部長 公共施設の場合、土砂災害計画などの基準を満たす必要がある。想定人数の見直しのあと直ちに増やすのは難しい。町内会が開設する施設もあるので、不足を解決するためには県と協議して進めたい。
指定避難所への冷暖房設備の整備について
総務企画部長 屋内37のうち、各学校体育館、奈留総合体育館12箇所。多額の費用で財政課題が大きい。小中学校は空調整備されている学校に避難させた。なるべく快適に過ごせるように努めたい。
田口 事前に避難所の整備をすることが、安心安全な島づくりである。国際基準の遵守は自治体の義務とされる。経済的理由を言い訳にするわけにはいかないと思っている。
熱中症対策について
学校施設における熱中症対策について
田口 一部の特別教室を除いてほぼ終了したと思おうが進捗は。
教育総務課長 普通教室は全て設置されているが、未設置の特別教室は家庭科・図工室などがある。優先順位を決定して統廃合のエアコンを移設する予定。設置ができない教室は必要に応じて設置する。
田口 早めの全教室設置をお願いする。体育館への設備設置依頼。NH Kで熱中症対策会議を開き、設置の支援や呼びかけをするように通達。園田市長が体育館や武道館にエアコンを設置するとあった。これらに対して五島市の考えは。
教育長 特別教室へのエアコンを先に行いその後体育館を考えているが、まだいけない状況。福江小学校の概算見積もりでは2億8千万円かかると。促進する方針を定めて特例交付金を指定。設備費用・維持管理負担が大きい。県外の先行実施に向けて考えて行きたい。
田口 運動場に冷水機の設置をお願いしたいが考えは。
教育総務課長 水道確保でき屋根・電源をとれる条件があり多額の不安・管理をする学校の負担が増えることから考えていない。
田口 自販機の設置依頼。水筒やペットボトルを何本ものむ。課題があると思うが五島市の考えは。
教育総務課長 様々な問題があるため考えていない。
田口 子供の生命に関わることなので一緒に考えていきましょう。
畜産施設における熱中症対策への支援について
田口 気象庁の発表では100年で2度以上昇。牛や豚の厚さ対策の重要性年々高まっている。厚さの影響は。
産業振興部長 R4こうし4頭・・・R7もコウシ2頭、セイ牛も死んでいる。
田口 市場価格低迷・資材高騰で厳しいく生産者には痛手。経営安定を目指すために支援制。
産業振興部長 既存の牛舎でも利用可能。厚さ対策への意識は高い。
田口 品質向上のための整備が不可欠。厚さ対策では管理面のサポートが必要。指導状況は。
産業振興部長 十分な飼育スペースを確保することが。熱源を確保すること、消化の良い餌を与えることが示されている。熱中症を一度発生するといくら良い餌を食べされても食べない。まずは病状の回復措置が求められる。引き続き関係機関の助言を受けて対策に取り組んでほしい。
老朽家屋・空き家の解体について
老朽家屋・空き家の現状と解体促進の取組について
田口 人材育成の観点からも管理の指導をしていただき、厚さの被害0を目指してほしい。空き家の状況について戸数と動向を。
建設管理部長 R7年3月末 2000戸数あまりで増えている。各地区の数字の紹介・・・。
田口 要因は
建設管理部長 空き家が増える詳細分析はしていないが、人口減少、老朽化による転居など。子息の転出も要因の一つ。実態意向調査を行い、亡くなったためが大半。入所や長期入院も理由。
田口 解体しない理由は、固定資産税が上がるとの声があるが、本当か。減税策はないのか。
市民生活部長 地方税法の特例があり、6分の一から3分の1に軽減される。住宅の用地の税負担を軽減する場合に設置される。適用が外されるため、3割減になる可能性がある。減税は地方税に書かれているで難しい。
田口 空き家の解体補助は
建設管理部長 個人が所有する建物は自らが処分することが前提。対応しない空き家で地域住民の生活を脅かす場合は、市が解体を行うケースもあり得る。
田口 何らかの手立てや予定を検討すべき。
主要地方道富江岐宿線におけるバス停と歩道の整備について
富江町の宮下バス停周辺の整備について
田口 富江の鳥居前の歩道のことだが、現在県道の拡幅工事が行われている。バス停待合所が設置されている。設置場所が県道沿いだが、撤去に至った経緯は。
建設管理部長 長崎県が行い関係団体に伺ったところ、宮下待合所は有志団体が建設したが、管理者が不明。地域町内会とバス事業者に今後の管理も含めた協議を行なった。現在は木製ベンチだが、許可を得て設置した。
田口 バス停の所有者が特定できないという事だが、設置した後数年間は使用している。バス会社も県も、それを立っているということは理解している。所有権云々よりも工事で撤去して復元しないのはいかがなものか。話し合いもして決定したのであれば致し方ないが、何か手が打てないのかと思っている。住民は切望していると要望している。熱中症対策の観点からもできないか。
建設管理部長 撤去に関して、地域に配慮して地元の意向も確認した上での判断としている。この決定は致し方なかったと考えている。
田口 歩道について道路線形に設置するがこの歩道は松林に造られている。経緯は。
建設管理部長 富江から岐宿を向いて左側には保安林区域の指定を解除する必要があった。時間も要することから、歩行者の空間の確保を図った結果、現状のようになった。
田口 見通しが悪く夜間は危険。照明施設の設置ができないか。松をきれば良かったが、人間よりも松を優先させたのかと思う。検討をしていただきたい。滑って危ないという事やマムシも心配されている。
建設管理部長 照明施設の必要性を認識しており協議検討中。
田口 県への働きかけをお願いします。
地区別懇談会について
地区別懇談会の開催状況と必要性について
田口 開催状況は。
総務企画部長 以前は市の幹部も出席して懇談会をしていたが、固定化していたので見直しを行い、「市長がお邪魔します」を開催している。コロナの影響もあり年に3回。残り半年だがたくさんの声に傾けるために可能な限り多く開催したい。
田口 市長も就任から1年を経過するが、選挙公約の実現をどう考えているか。たくさんの声に耳を傾ける、大丈夫ですよ、全部任せてくださいと述べているが、市民の声を反映するには懇親会や座談会が必要と思うがどうか。
市長 懇談会の開催や大変意義のあるものだと考えている。7月9日に奈留保健センターで民生委員の方とのお話。7月10日は嵯峨島漁村センターに行った。買い物や草払いに苦労していると。竹が伸びるのが早く、女岳の方に行ったが大変だろうと思った。各地の実情を知る良い機会となった。懇談会に限らずいろんなイベントにも出席している。たくさんの意見や要望を頂いている。多く会って話をして担当課に繋いでいきたいと思っている。今後ともきちんと出席したい。
田口 市民の声を聞くことに関連して、6月に若者三人からただかり山の陳情項目で市民の声を広く反映する場を設けること、関係団体の意見を取り入れることとあったと思う。どのように対応しているのか。
富江支所長 市民の声を広く反映する部分は町内会などの組織である街づくり協議会が適していると判断。陳情内容や現在の施設の状況の意見交換を行なった。全団体の対象に意見交換を行い広く意見を求める。
田口 市長は時間の許す限り会合に出席していると聞いている。市長答弁にあったお邪魔しますを積極的に開催して、一人でも多くの方の声を聞いてほしい。ぜひ富江にもお越しいただき、直接耳を傾けていただきたい。