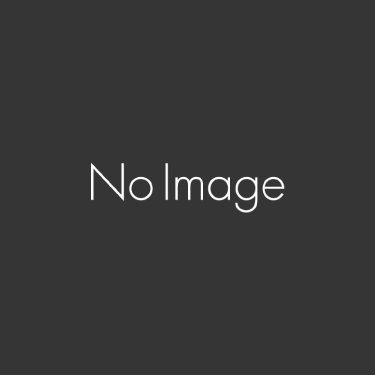本事業の中身を私なりに解釈すると
900万円をかけて、既に裁判判決が出ている12年前の事件の調査を行い、再発防止に努める
という予算ですが、私はその必要性が今ひとつ理解できません。
過去の経緯
本質的には組織のガバナンスの問題です。
五島市行政は今まで、第三者委員会を設置することなく行政運営をしてきました。
その是非はともかくとして、出口市長になって初めての第三者委員会という判断です。
改めてですが、H29の件で2021年の議会で野口元市長はこう述べています。
元長寿介護課の職員が、令和2年10月28日に窃盗の疑いで逮捕された件について、4月27日、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。
この公判において、元職員が在職中も被害者のキャッシュカードを不正利用し、現金を引き出していたことが判明しました。
すでに亡くなられた被害者の方とそのご遺族の皆様に心からお詫び申し上げます。
市民の健康や暮らしを守るべき職員がこのような不祥事を起こしたことは痛恨の極みであり、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。本来であれば、懲戒免職処分となるべき事案でありますが、退職した職員は処分することができないため、すでに支給した退職手当の全額返還を求める手続きを執っております。
事件発生当時の元職員の上司についても、すでに全員が退職しており、五島市としての責任を明らかにし、自らを戒めるため、私と副市長の給料の減額を行う条例改正案を本議会に提案しております。
今後、このような不祥事が二度と起きないよう、全職員を対象とした服務・倫理研修の実施や不祥事防止のための行動指針の作成、法令違反通報に係る外部相談窓口(弁護士)の設置など再発防止策を講じ、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
で、私は減給に対する賛成討論で以下の通り述べています。
10番(中西大輔君) おはようございます。私は議案第52号に対して賛成討論をいたします。
今回の議案の焦点は、減給額とその期間が過去の事例と比較して妥当であると言えるかどうかということだと考えます。五島市では平成20年度に職員による飲酒運転の不祥事に関して自らを戒めるために、市長及び副市長の給料の減額を1か月間、30%としています。五島市の過去の事例と比較して今回の不祥事に対し、先例及び前例を元に当該減額について判断したものであるという答弁がありました。過去の事例と比較すると、今回の減給の総額は、過去最も重かった処分の5倍の金額であるため十分であると判断できます。
しかしながら、私は金額云々の問題ではなく、再発防止策の徹底というところが大事であると考えます。
今回の事件は、市民の行政に対する信頼を失墜させる極めて重大な事件だと思います。議会初日の市政報告では、全職員を対象とした服務・倫理研修の実施や不祥事防止のための行動指針の作成、法令違反通報に係る外部相談窓口の設置など、再発防止策を講じるということでした。
特別職に対する条例の整備とともに、再発防止に向けた取組を確実に実践していただいて、市民の信頼を取り戻すためにも賛成討論といたします。
つまり、形式上はH29年度の件に対する「再発防止策」は完了している訳であり、改めて今回その問題を掘り下げるという事は、既に実施した対策のどこが不十分だったのか、明らかにする必要があると感じます。
第三者委員会設置に対する疑問
第三者委員会の設置に対する主な疑問は以下の通りです。
① 実効性の低さ(12年前の事件の再発防止)
再発防止策は通常、事案発生直後に迅速に講じてこそ意味があるものです。12年以上経過した事案について再度調査し、報告書を作成しても、既に多くの関係者が退職しており、組織文化も変化しているため、具体的な改善に直結する可能性は低いといえます。
② 裁判を通じて事実関係はほぼ明らか
既に民事訴訟で事実認定がなされ、判決文が公開されているなら、第三者委員会が改めて「事実関係」を調査する必要性は低いです。
③ 費用対効果に見合わない
市長自らが対策を考案した方がスピード感を持って実行できる
既に事実認定済みである以上、新たに中立的調査は不要で、実行フェーズに移るべき
外部委託費9,130,000円の費用に見合う効果は低い
市長が現状の組織体質に疑問を抱いているならば、高額な委員会設置ではなく、既存の監査委員会や市長直属チームで足りるのではないでしょうか。
④市の裁判での主張との整合性
裁判での主張や証拠集めを通じて、既に事実関係の調査は完了しているはずです。
その中で市は、H25の事件に関して「業務上関係がない(=使用者責任は認められない)」と訴えています。そうであるならば、組織としてガバナンスの範囲外の出来事なので、再発防止策も取りようがないはずです。
再発防止策を講じるという事は、組織のガバナンスの内側の事なので、使用者責任を認めるという事になります。
この論理矛盾に対する説明が欠けているように感じます。