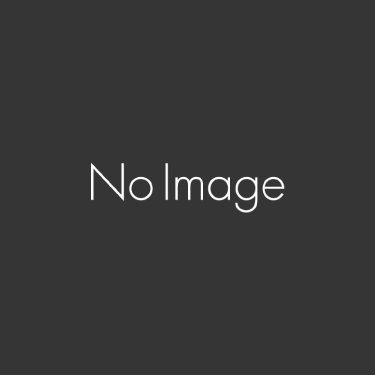海鳥と私
ここは小高い丘の上。標高が300メートルもある見晴らしの良い場所で、天気が良い日は町と海が一望できる。私はそこで、毎日足を運んで、ある「習慣」を続けている。島の向こうからやってくる海鳥たちとの会話だ。私が笛を吹くと大小の鳥たちが海の向こうから集まり、羽を休めて世間話を始める。その半分以上は、鳥たちの生活に関するものだ。
「最近始まった護岸工事のお陰で、新しい家が壊されてしまったのよ。」
とか、
「ここ数年は暑くて、昔ほど沢山の魚を見かけなくなったわ。」
といった話だ。鳥たちが被る影響の大半は、人間の都合によるとばっちりだ。私は鳥たちの苦情を聞きながら、人間として知りうる限りの情報を、鳥たちに教えることにしている。
「南町の集落で、大規模な工事が計画されているから、早く移ったほうが良いよ。」
とか、
「向かいの島が無人島になる予定だから、子育てにはいいかもね。」
といった人間の動きだ。鳥たちを取り巻く環境は決して楽ではないけど、彼らは賢明に生きていて、雛が無事に巣立った話や、パートナーが見つかった話など、明るい話もしてくれる。私はそうした「海鳥の生活」を聞くことを毎日の習慣としている。
私が鳥たちと会話するきっかとなったのは、漁師をしている父親の影響だ。余って売り物にならなくなった魚を、どうにか処分しなければいけない。だけど家の周りには、魚を食べるような動物はいない。そこで試しに丘の上で、海鳥たちに魚の残りを与えることにしてみたのだ。始めのうちは、全く見向きもされなかったのだが、次第に鳥たちの間で「餌をもらえる」という口コミが広がり、人気となった。そしていつしか、餌を貰うことよりも「人と話をすること」が、鳥たちの間で普及していった。私も朝の週間として、鳥たちの話を聴くのが楽しみになっていった。鳥たちとの日常会話は、私だけに与えられた特権なのかもしれない。
そんなある日、一人の老人が丘のふもとにやってきた。見たこともない姿だが、よぼよぼで杖を持って歩いている。散歩だろうかと思ってしばらく見ていると、飛来した海鳥たちが、少しずつおじいさんの周りに集まっている。遠くにいるから何を話しているのかは聞こえない。ただその様子を見ていると、どうやら私と同じように、おじさんは鳥たちと会話をしていることが分かる。それからおじいさんは毎日、丘の上に現れるようになった。ちゅんちゅん、ぴよぴよ、キーキーと。日を重ねるにつれて、おじいさんの周りに集まる鳥たちの種類と数が増えている。一方で、私の周りに集まっていた鳥たちの数は減り、徐々におじいさんの方に集まるようになってきている。
私は次の日から、持って来る餌の量を、わざと増やすようにしてみた。腹を空かせた鳥たちは、早朝からのご馳走に喜ぶだろう。そう思って餌を与えるのだが、鳥たちは餌をつまむと、そのまま私の元から去って行って、おじいさんの方へと向かってしまう。
一体どうして?
おじいさんには、何か特別な力があるの?
しかしおじいさんは、ただ杖を持ってゆっくりと歩いているだけ。特に餌を与えるわけでもなく、自然と鳥たちに囲まれている。その様子を遠くから眺めていると、鳥たちと交わした何気ない日常の楽しみが、もう遠い昔のことのように感じられてしまった。そして私だけ、変わり続ける世界の片隅で、ぽつんと取り残されてしまったような気持ちがした。
どうしたらいいのだろう。丘の上り口には、丁度「通行止」と書かれた立て札とチェーンが横たわっている。私はそれを、わざと次の日から上り口に備え付けてみた。看板があれば、それを除去してまで登ろうとはしないだろうし、丘に上がらなければ鳥は見えない。これでどうなるだろうか、見てみよう。いつもの時刻におじいさんが来る。私は隠れながら、固唾を呑んで状況を観察している。おじいさんは立て札の前まで歩いていき、その前で立ち止まる。数秒間、時計が止まったと思ったら、おじいさんは残念そうにきびすを返して帰っていった。
私は意気揚々と、立て札を元の位置に寝かせ、丘の上にかけ上って景色を見渡した。いつものように笛を吹くと、数匹の海鳥たちが早速集まってきた。そう、ここは誰に邪魔されない、私だけの空間。私は以前と同じように、鳥たちとの会話を楽しむ。次の日からも、毎日同じ作戦を決行し、私は再び自分だけの空間を楽しむことが出来るようになった。そんなあるとき、一羽の海鳥に尋ねてみた。
「ここのところ、生活に困っていることはない?」
海鳥は険しい顔をしてこう言った。
「この丘の通行止がいつ終わるのか、それが一番の心配です。」