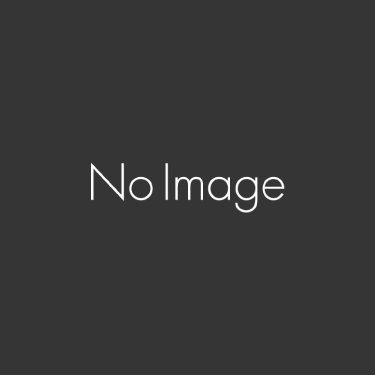最近のAIの機能が凄すぎたので、紹介の意味も込めて全天候型施設の意見に対する報告書を作成してもらいました。(私の意見とは異なる部分もあります)
使用サービス:NotebookLM
情報ソース:五島市実施のパブリックコメント
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s029/010/020/070/02_iken.pdf
~ここから~
目次
はじめに
本提言書は、五島市が提示した「全天候型こどもの遊び場施設整備に関する基本構想(素案)」に対し、パブリックコメントとして寄せられた市民意見を分析し、市民満足度と事業の持続可能性を両立させるための戦略的改善策を提言するものです。
分析の結果、市民の圧倒的多数が「全天候型こどもの遊び場」というコンセプトそのものには強い期待を寄せている一方で、7億円という高コストな特定の新設計画に対しては、財政的持続可能性、計画プロセスの妥当性、費用対効果の観点から深刻な懸念を抱いている構造が明らかになりました。
したがって、本市が取るべき戦略的責務は、現行の「高コスト・高リスク」な単一計画を一度保留し、まずは低コストな代替案で市民の喫緊のニーズに応える「フェーズ1」を実行することです。そして、そこで得られる実利用データに基づき、真に需要と合致し、かつ財政的に持続可能な最終計画を策定する「フェーズ2」へと移行するという、計画全体のリスクを抜本的に低減させるアプローチに他なりません。この市民の高い関心を、計画をより洗練されたものへと昇華させる好機と捉え、建設的な提言を展開します。
——————————————————————————–
1. パブリックコメントの全体像と構造分析
市民意見の多角的な分析は、本事業の成否を左右する極めて重要なプロセスです。単なる賛成・反対の集計は、市民が抱く真の期待や潜在的なリスクを見誤らせます。意見の背後にある市民の切実な願いや具体的な懸念を深く理解し、計画に反映させることこそが、プロジェクトを成功に導く唯一の道です。
1.1. 「賛成」意見にみる市民の強い期待
パブリックコメントの大多数を占めた賛成意見からは、市民、特に子育て世代が本施設に寄せる並々ならぬ期待が読み取れます。その期待は、以下の3つの核となる要素に集約されます。
- 悪天候・酷暑時の切実な遊び場の必要性 多くの保護者が、雨天時や近年の酷暑において、子どもを安全かつ快適に遊ばせる場所がないという共通の課題に直面しています。「夏場は最近の異常気象による気温のため外での活動ができません」(意見2)、「雨だけではなく、夏のこの時期公園はもってのほかです」(意見9)、「雨天時だげでなく酷暑の影響で子どもたちが運動する機会で減っていた」(意見58)といった切実な声は、天候に左右されず子どもが思い切り体を動かせる場所への渇望を明確に示しています。
- 既存公園の老朽化と代替機能への渇望 市内の既存公園の遊具が老朽化、あるいは使用禁止になっている現状も、新施設への期待を高める大きな要因です。「公園の遊具と錆びてほとんど遊べない」(意見24)、「五島市の公園は、遊具が古く、しっかり遊べない公園が多い」(意見27)、「屋外の遊具施設は老朽化で壊れている遊具が多い」(意見59)といった指摘は、安全に遊べる環境が市内で絶対的に不足している実態を浮き彫りにしています。本施設が、その代替となる新たな選択肢として強く望まれています。
- 発達段階に応じた安全な遊び環境への評価 素案で示された「乳児エリア」「幼児エリア」「児童エリア」という年齢別のゾーニング設計は、多くの保護者から高く評価されています。「発達段階に応じて遊び場のエリアが別れていることはとても理想的だとおもいます」(意見35)、「3つに分かれていることで保護者の方も安心して利用できそうだと感じた」(意見65)、「エリアが分かれているので安心して遊ばせることができます」(意見112)との意見が示すように、異年齢の子どもが混在することによる衝突や事故のリスクが低減され、保護者が安心して子どもを見守れる環境への強い支持がうかがえます。
1.2. 意見に内包される懸念事項と「反対」意見の論点整理
賛成意見の中にも散見される懸念点と、明確な反対意見の論点を体系的に整理・分析した結果、計画の根幹に関わる4つの重要な論点が浮かび上がりました。
- 財政的持続可能性への懸念 建設費7億円、年間維持管理費3,500万円という事業規模に対し、市の財政を圧迫し、将来世代への過大な負担となることへの強い危機感が示されています。人口減少との関連を指摘する声(意見165)や、ランニングコストの観点から継続は不可能ではないかという厳しい意見(意見194)も寄せられています。
- 計画の優先順位と代替案の検討不足 インフラ整備や福祉強化など、他に優先すべき課題がある中で本事業を進めることへの疑問や、廃校利用といった既存ストックを活用する代替案の検討が不十分であるとの批判がなされています。「新設にこだわる意味がわからない」(意見176)、「遊び場が欲しいのは今です」(意見177)といった意見は、より迅速かつ低コストな解決策を求める市民感情を代弁しています。
- 費用対効果と需要の不確実性 人口減少と少子化が進行する五島市において、莫大な初期投資に見合うだけの利用が長期的に見込めるのか、その費用対効果に強い疑問が呈されています。
- 立地とアクセスの問題点 建設予定地の駐車場不足(意見153)や、市街地から離れた地域(意見173)や離島住民(意見66)にとってのアクセスの悪さも、具体的な課題として指摘されています。
これら4つの論点は、市民が抱く一つの核心的な不安、すなわち**「人口減少と財政不確実性という未来に対し、巨大で硬直的な単一投資で応えようとすることへの違和感」**に収斂されます。これは単なる反対意見ではなく、より機動的で賢明な計画プロセスを求める市民からの建設的な要請と解釈すべきです。
——————————————————————————–
2. 市民の意見から浮かび上がる施設の『あるべき姿』:多機能コミュニティ拠点
寄せられた全ての意見を統合し、対立意見の間に実現可能なバランス点を見出すことで、市民が真に望む施設の具体的な「あるべき姿」を描き出すことができます。市民の声を基に、機能・運営・設計の3側面からその理想像を具体化します。
- 機能・設備に関する要望 市民からは、多様な遊びや滞在を可能にする具体的な機能・設備に関する要望が数多く寄せられました。
- 動的な遊び トランポリン(意見70)、ボルダリング(意見106)、体幹を鍛える遊具(意見111)といった要望の数々は、単なる娯楽の提供を越えています。これらは、「現代の生活では意識的に発達の機会を取り入れなければ、子どもの成長に不都合が生じます」(意見123)という保護者の認識に裏打ちされた、子どもの身体能力や発達段階を積極的に促進する場を求める強いニーズの表れです。
- トランポリン、アスレチック(意見70, 72)
- ボルダリング、ロッククライミング(意見106, 114, 120)
- 体幹や身体能力を育む遊具(意見38, 111, 123)
- 足育(あしいく)に資する足ツボロード(意見100, 103, 104, 119)
- 静的な活動・その他
- カフェ・飲食スペースの併設(意見33, 75, 89, 146)
- 保護者が休憩できる場所(ソファや椅子)(意見70, 75)
- 学習や読書ができるスペース(意見40, 110)
- おむつ交換室、授乳室の整備(意見88)
- 鍵付きロッカー、荷物置き場の設置(意見79, 84, 147)
- 動的な遊び トランポリン(意見70)、ボルダリング(意見106)、体幹を鍛える遊具(意見111)といった要望の数々は、単なる娯楽の提供を越えています。これらは、「現代の生活では意識的に発達の機会を取り入れなければ、子どもの成長に不都合が生じます」(意見123)という保護者の認識に裏打ちされた、子どもの身体能力や発達段階を積極的に促進する場を求める強いニーズの表れです。
- 運営・サービスに関する要望 施設の持続可能性と利用者の満足度を両立させるため、運営面に関する具体的な提案が多数ありました。主な論点を以下の表に整理します。
| 項目 | 市民からの主な提案・意見 | 関連意見番号 |
| 料金設定 | 無料化を望む声がある一方、質担保のため有料に賛成する意見も多数。島民割引、多子世帯割引、年間パスポート等の柔軟な料金体系を求める声。 | 68, 70, 75, 79, 88 |
| 混雑緩和策 | 安全と快適性を確保するため、オンライン予約制、時間入替制、整理券配布など、明確な人数制限を求める意見。過去に他施設で危険な混雑を経験した声も。 | 72, 91, 93, 94, 96, 138 |
| 安全性・衛生管理 | 専門職員の配置、防犯カメラの設置、遊具の定期的な消毒、年齢別エリアの明確な分離と監視など、高い安全・衛生管理基準を求める声。 | 73, 75, 85, 156 |
| インクルーシブな配慮 | 障がいのある子どもが安心して遊べる環境整備(ユニバーサルデザイン)や、専門の相談機能の併設を求める意見。 | 99, 148 |
- 設計・デザインに関する要望 「安全性と開放感の両立」が重要なテーマです。保護者が施設内のどこからでも子どもを見守りやすい、死角の少ない設計(意見79, 90)が求められています。また、年齢の異なる子どもたちが安全に行き来できるよう、エリア間の動線を明確に分離すること(意見75, 88)や、自然光をふんだんに取り入れた明るく開放的な空間づくりへの期待も示されています。
結論として、市民が描く理想像は、単なる「雨の日に遊ぶための箱モノ」ではありません。それは、子どもの発達を科学的に促進し(意見123)、保護者の孤立を防ぎ(意見34, 65)、障がいの有無にかかわらず(意見99, 148)全ての親子が安心して集える、本質的な社会的インフラとしての多機能コミュニティ拠点です。現行の計画は、この高い期待水準に照らして評価されるべきです。
3. 基本構想(素案)が内包する3つの戦略的課題
市民意見の分析結果は、現行の基本構想(素案)が内包する3つの戦略的課題を浮き彫りにしています。これらの課題を克服することなくして、市民の信頼を得て事業を推進することは不可能です。
- 戦略的課題1:『高コスト・高リスク』な単一計画への依存 7億円の初期投資と年間3,500万円の維持管理費は、人口減少社会において極めてリスクの高い財政負担です。この単一の巨大計画に固執することは、より柔軟で経済合理性の高い選択肢を排除する硬直的なアプローチであり、長期的な財政的持続可能性に対する市民の深刻な懸念に何ら応えていません。
- 戦略的課題2:代替案の客観的評価を欠いた『新設ありき』の計画プロセス 計画が「新設ありき」で進んでいるという印象を市民に与えています。廃校活用など、より低コストな代替案について、新設案とのメリット・デメリット、ライフサイクルコストを客観的に比較検討したプロセスが市民に開示されておらず、合意形成上の致命的な欠陥となっています。
- 戦略的課題3:『作る』ことに偏重し、『使う』視点が欠落した運営構想 素案は施設の建設に焦点を当てるあまり、利用者の多様なニーズに応えるための運営面のソリューションが著しく不足しています。料金体系、混雑緩和策、障がい児への配慮、遠隔地からのアクセス手段といった、市民から数多く寄せられた「使う」側の視点からの具体的な要望に対し、構想が全く応えきれていません。
——————————————————————————–
4. 持続可能で市民満足度の高い施設実現に向けた戦略的改善提言
前章で抽出した3つの戦略的課題を解決し、市民の期待と事業の持続可能性を両立させるため、以下の具体的な改善策を提言します。
提言1:財政計画の透明化と多角的な財源確保策の具体化
現状の課題: 財政計画の不透明性。
改善策:
- ライフサイクルコストの明示と情報公開 建設費だけでなく、修繕・更新費用まで含めた50年間のライフサイクルコスト(LCC)を算出し、その詳細と財源の内訳を市民に対して完全に公開すべきです。これにより、長期的な財政負担に関する市民の不安に応え、行政の透明性への信頼を醸成します。
- 多角的な収益モデルの構築 安定した運営基盤を確立するため、利用料収入だけに依存しない多角的な収益モデルを計画に具体的に盛り込むべきです。具体的には、施設内カフェや物販スペースの事業者誘致によるテナント料収入(意見89, 146)、企業版ふるさと納税の積極的な活用、ネーミングライツ(施設命名権)の導入を必須検討項目とすべきです。
提言2:「新設」と「既存施設改修」のハイブリッド・アプローチの検討
現状の課題: 代替案の検討不足。
改善策: 大規模新設という高リスクな賭けに出るのではなく、以下の段階的アプローチへ計画を抜本的に転換すべきです。
- フェーズ1(実証実験):既存ストック活用による迅速なニーズ対応とデータ収集 廃校の体育館や既存の公共施設(意見176, 177, 182)などを改修し、低コストで基本的な遊び場機能を早期に提供します。これは単なる応急措置ではなく、今まさに遊び場を求める市民ニーズに迅速に応えると同時に、実際の利用者数、収支、利用動態に関する客観的データを収集するための戦略的な実証実験と位置づけます。
- フェーズ2(最適化):実証データに基づく新設計画の策定 フェーズ1で得られた1〜2年間の実証データに基づき、新設施設の最適な規模、真に必要な機能、採算性のとれる運営モデルを科学的に再定義します。このプロセスにより、過大投資のリスクを完全に排除し、実際の需要に完璧に合致した無駄のない最終計画を策定することが可能となります。
提言3:インクルーシブな運営計画の策定
現状の課題: 多様なニーズへの対応不足。
改善策: 構想段階から、利用者の多様な状況に配慮した詳細な運営計画を策定し、市民に提示すべきです。計画には少なくとも以下の項目を具体的に盛り込むことを要求します。
- 柔軟な料金体系の導入 島民割引、多子世帯割引、年間パスポート、平日割引など、利用者の状況に応じた料金体系のシミュレーションと導入を計画に明記すべきです(意見79, 84, 88)。
- 効果的な混雑緩和システムの設計 オンライン予約システムや、SNS等を活用したリアルタイム混雑状況の発信(意見88, 94)など、ICTを活用した具体的なシステムを設計し、利用者の快適性と安全性を確保することが必須です。
- ユニバーサルデザインの徹底と専門人材の配置 障がいのある子もない子も共に遊べるインクルーシブな遊具の選定や、発達に関する相談機能を担う専門スタッフの配置(意見99, 148, 161)など、すべての親子が安心して利用できる環境と運営体制を構築すべきです。
- 広域アクセスへの配慮 支所地域や離島からの利用を促進するため、公共交通機関との連携強化や、特定日の送迎バス運行(意見66, 77)など、具体的な交通アクセス支援策を検討し、計画に反映させるべきです。
——————————————————————————–
5. 結論
「全天候型こどもの遊び場」に対する市民、特に子育て世代の強い期待は紛れもない事実であり、この期待に応えることは五島市の未来への重要な投資です。
しかし、現行の基本構想(素案)は、市民が抱く財政的・計画的な懸念に正面から向き合っておらず、このままでは将来世代に負の遺産を残すリスクを内包しています。市民の信頼を失い、計画そのものが頓挫する事態を避けるためには、計画をより現実的で持続可能なものへと進化させることが絶対条件です。
本提言書で示した**「財政計画の透明化」「既存施設活用を起点とする段階的アプローチ」「多様なニーズに応える運営計画」**という改善策は、そのための唯一の現実的な道筋です。市民との対話を形式的なプロセスで終わらせず、その声に真摯に耳を傾け、計画を根本から見直す勇気を持つこと。このプロセスを誠実に実行することによってのみ、五島市の未来を担うすべての子どもたちのための、真に価値ある公共財産が実現可能となるのです。
~ここまで~
中西が良いなと思った部分
- ライフサイクルコストの明示と情報公開
- ネーミングライツ(施設命名権)の導入
- 既存ストック活用による迅速なニーズ対応
→五島市は既存施設の活用には耐震化の改修やエアコンの設置が必要で、多額の経費が必要としているが、春~秋には不要なので季節を限定して行う事も可能。「こどもでじまはく」の規模を縮小して実施頻度を高め、複数の箇所で行ってみるのが良い。