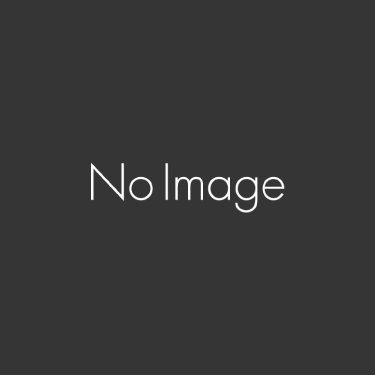出口市長の所信表明の続きです。
人を育て、輝く、学びの“しま”をつくる
【結婚・出産・子育ての支援】
少子化については、国においても最大の危機と捉えており、児童手当の拡充や出産・子育て応援交付金など、様々な取組をこども未来戦略「加速化プラン」として重点的に行っております。
五島市においても、このプランを着実に実施しながら、結婚、出産を希望する若い世代が安心して子育てができるよう、出会いから結婚・妊娠・出産・子育てのライフステージに応じた切れ目ない支援を強化してまいります。
五島市では、子ども施策に関する基本的な方針や具体的施策などをまとめた「第3期五島市子ども・子育て支援事業計画」を年度内に策定する予定としております。計画期間を5年間とし、関係機関と連携しながら取組を推進してまいります。
出会いの支援については、これまで、結婚を希望する若者が素敵な出会いから結婚へつながるよう、民間業者と連携した婚活イベントを実施してまいりました。今後は、これまで以上に参加を促していくため、より気軽に参加できる出会いの場を創出してまいります。
併せて、出会い・結婚の総合窓口である結婚支援センターの運営を継続し、お付き合いに不安、悩みがある独身男女のきめ細かなサポートを実施してまいります。
結婚後の支援については、新婚世帯への家賃・引っ越し費用・リフォームなどの助成を継続しながら、若い世代の経済的負担を軽減してまいります。
また、子どもを授かることが難しい方へは、島外での不妊治療にかかる治療費や交通費、宿泊費の助成を行ってまいります。
妊娠期からの支援については、令和6年4月にこども未来課内に「こども家庭センター」を設置し、妊娠期から産後、子育て期における全ての妊産婦、子ども、子育て家庭に対し、切れ目のない支援に努めてまいりました。
最近では、特に子どもの発達や養育に関する不安や悩みを抱える保護者が増えております。今後は、乳幼児相談や健診の機会に言語聴覚士や作業療法士による育児アドバイスを気軽に利用できる機会を設け、母子の健康管理や子どもの発達を促す支援に、より一層取り組んでまいります。
また、少子化の進行による地域での関係性の希薄化やコロナ禍の影響による子育て家庭の孤立など、地域で子ども・子育て家庭を見守る力、育む力が低下しております。今一度、保育所や小中学校などの関係機関と連携し、「親の子育て力」が向上するような講座や学ぶ機会を創出しながら、全ての子どもの健やかな成長につながるよう支援してまいります。
デジタル化の推進については、国において、母子保健情報を本人と医療機関、自治体との間で迅速に共有・活用していくための情報連携基盤が整備され、令和8年度から全国で運用する予定です。
こうした動きに連動して、五島市では、令和7年度に電子版母子健康手帳を導入することとしております。これまで紙で行っていた乳幼児健康診査の通知や問診票のデジタル化を進め、妊婦・子育て家庭の利便性の向上を図ってまいります。
乳幼児、子ども福祉医療費の助成については、3歳未満児の無償化をはじめ、高校生までの助成対象の拡大、ひとり親家庭などの子どもに対する無償化など、段階的に制度を見直し、子育て世帯の負担軽減に努めてまいりました。
令和7年度からは、助成方法を見直し、これまで未就学児までが対象 となっていた申請の必要がない現物給付方式を中学生まで拡大する予定としております。これにより、窓口での支払いは、1日につき800円、月では1,600円までとなります。
実施については10月からを予定しており、今後、関係機関との調整やシステム改修などの準備を進めてまいります。
喫緊の課題である保育士の人材確保については、令和7年度から新たな取組として、保育士養成学校の新卒者や保育士免許を有しているものの保育施設に就労していない「潜在保育士」の就職支援を目的とした就労応援金制度を創設したいと考えております。
このほか、保育の質を向上させるため、園内研修の充実や研修機会の増加に向けた取組を進めるとともに、保育士が保育以外の業務を行う時間である「ノンコンタクトタイム」を確保するための支援を行うこととしております。
保護者の就労の有無にかかわらず、保育施設を定期的に利用することができる「こども誰でも通園制度」については、令和8年度からの本格実施に向け、情報発信や制度の理解促進に努めるとともに、先進事例を参考にしながら市内保育施設との協議を進めてまいります。
雨の日でも遊べる子どもの遊び場づくりについては、子育て世帯へのニーズ調査をはじめ、他自治体の事例研究など、事業着手に向けた準備を進めております。計画の基本的な概要については、年内に公表する予定としております。
また、令和6年9月に開催した子ども向け大型遊具を設置したイベントを令和7年度も引き続き開催し、子ども達が思い切り身体を動かし、保護者が交流できる機会を作ってまいります。
福江総合福祉保健センターについては、建設から25年以上が経過し、施設の大規模改修が必要な時期を迎えております。令和7年度に実施設 計を行い、令和8年度以降、計画的に改修していくことで、施設の長寿命化を図ってまいります。
【教育のしまづくり】
令和6年度の市内小中学校の児童・生徒数は2,107人で、平成1 7年度の4,291人から2,184人減少しており、19年間でほぼ半減しております。
このような中、複式学級の解消や集団学習に必要な一定の学校規模を維持するため、保護者との協議・調整を進めておりました盈進小学校については、協議の結果、令和10年4月に富江小学校と統合したいと考えております。
また、統廃合の検討基準に該当する奥浦小学校についても、引き続き関係者と協議・調整を進めてまいります。
ふるさと教育については、全ての小中学校で地域資源を活用した体験活動を引き続き実施してまいります。また、ふるさと活性化貢献支援事業では、令和7年度は市内小中学校、高校のうち12校を指定校に位置付け、子ども達が自ら少子化、人口減少などのふるさとが抱える課題を捉え、その解決に向けて学習する活動を支援してまいります。
今後も、ふるさとについて学ぶ機会を拡充しながら、ふるさとを誇りに思う心を醸成し、一人でも多く五島市の活性化に貢献できる人材を育成してまいります。
不登校をはじめ一人一人に応じた支援体制づくりとして、スクールソーシャルワーカーの配置時間を増加し、学校適応指導員を2人に増員しております。令和6年度からは教員業務支援員3人を配置しており、引き続き児童生徒、保護者、教職員へのサポートを強化してまいります。
学校教育環境の充実については、校舎照明のLED化、トイレの洋式化を順次進めております。また、学校給食施設については、調理員の人材不足や施設の老朽化も進んでおり、今後、学校給食の安定供給が懸念されることから、学校給食の提供体制の在り方や効率化について検討を進めてまいります。
物価高騰に係る小中学校保護者の負担軽減策として、食材の価格高騰により学校給食費が増加しているため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、高騰分の学校給食費の支援を実施してまいります。
中学校部活動については、学校部活動から段階的に地域クラブ活動へ移行できるよう地域クラブ認定の申請手続を開始しております。
令和8年度から、休日は完全に地域クラブへ移行できるよう、生徒のニーズに応じた地域クラブの設立、運営を支援していくとともに、活動を行う上で必要な環境整備に努めてまいります。
英語教育を推進し、グローバルな視点をもった人材育成を目指すプロジェクトGの取組については、これまでと同様に小学校1年生からの英語教育を推進するとともに、外国語指導助手(ALT)のネイティブな英語に触れながら学べる環境を充実してまいります。
洋上風車夢基金を活用したシンガポールへの中学生国外体験学習事業については、五島の将来を担う子ども達に生きた英語に触れる機会を提供するため、引き続き実施してまいります。
久賀島と奈留島で実施している「しま留学生受入事業」について、令和7年度は、久賀小中学校の全児童生徒12人中、しま留学生が11人、奈留小中学校では36人中4人となる予定です。
令和5年度に県が設置した「これからの離島留学検討委員会」の報告を受け、高等学校の離島留学同様、留学生やしま親が一人で悩みを抱え込まないような体制づくり、しま親の役割の明確化、子どもの状況や親の考えの事前確認方法などについて、しま留学連絡協議会を中心に見直しを進めております。
また、しま親の確保に努めるとともに、市内の高等学校が留学生にとって進学先の選択肢の一つとなるよう、中・高連携の強化を図りながら五島市の魅力を発信してまいります。
五島南高等学校と奈留高等学校の離島留学制度については、県立高校の存続及び地域活性化を図るため、県及び関係団体と連携し、ホームステイ先の確保や財政的な支援を引き続き行ってまいります。
【学びと成長のしまづくり】
令和7年9月に、国内最大の文化の祭典である第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭「ながさきピース文化祭2025」が県内全域で開催されます。
五島市では、東京藝術大学×世界遺産の島~セミナー&コンサートなどの地域文化発信事業や分野別交流事業として「連句」の全国大会を1 0月に開催することとしております。
ながさきピース文化祭開催の機運に合わせ、市民の皆様が文化振興への関心を深める取組を積極的に進めてまいります。
生涯スポーツの推進については、いつでも、誰でも、どこでも気軽にできるスポーツに関心を持つきっかけづくりとして出前講座を開催し、健康意識の向上や習慣化を図ってまいります。
また、五島市健幸アプリ「ぎばっと!」は、令和6年12月末に登録者数が3,000人を超えました。更に登録者数を増やすため、今後もアプリを活用したウォーキングイベントの開催や貯まったポイントを特典クーポンとして使える地元協力店の拡充などを図り、市民の皆様が運動やスポーツを楽しみながら健康づくりに取り組めるよう努めてまいります。