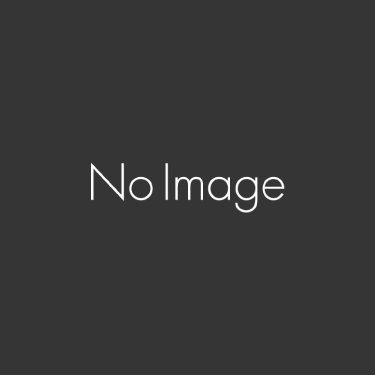出口市長の所信表明の続きです。
安全・安心な、魅力ある“しま”をつくる
【地域コミュニティの維持・活性化】
人口減少や高齢化の影響により、地域課題が多様化していることから、五島市では、地域との協働により課題解決に取り組む協働のまちづくり を推進しております。引き続き、まちづくり協議会などの地域活動団体の取組を支援するとともに、地域づくりイベントや地域づくりを支える人材の育成に向けた講演会・研修を実施してまいります。
地域おこし協力隊制度を各分野の課題解決に積極的に活用してまいり ます。令和7年度は、インバウンドの誘客促進、奈留島の観光商品企画、奈留島独自の子育て環境構築、空き家バンクの活用促進、農業の経営継承を目的とした新規営農者及び就農者の獲得の5つの課題への取組を強化するため、新たに9人の地域おこし協力隊の採用を予定しております。
地域振興に資する民間事業者の新たなビジネスについて、国の地域経済循環創造事業交付金、通称「ローカル10,000プロジェクト」を活用し、その立ち上げを支援してまいります。
令和7年度は、遊休施設を改修した宿泊施設や五島豚を原料とする食品加工施設の整備を予定しております。
【健康で長生きできる環境づくり】
保健・医療・介護・地域の連携により、自分らしく健康で生活することができる環境を整備し、市民の皆様の健康増進と医療費の増加抑制につながるよう努めてまいります。
医療体制の維持については、県や長崎大学と連携し、医師・看護師などの人材確保に努めるとともに、地域医療に関わる人材の育成に取り組んでまいります。また、令和7年度は、老朽化した黄島診療所を旧黄島小中学校の敷地内に住民センターと合築で整備してまいります。
巡回診療車両によるモバイルクリニック事業については、福江、玉之浦、岐宿及び奈留地区の6つの医療機関と連携して実施しており、令和 6年度は、1月末現在で延べ273人の患者がオンライン診療を受けております。
今後、利用可能な医療機関や地域を広げながら、移動に困難を感じている方が定期的に受診できる体制を整え、慢性疾患の重症化予防、健康寿命の延伸に努めてまいります。
介護人材の確保については、資格取得や復職の支援、離職防止を目的として、各種研修経費の補助事業を継続してまいります。また、介護福祉士養成校奨学金支援事業については、令和7年度から新たに福祉系高等学校を支援対象校にしたいと考えております。
医療・介護DXの普及・推進については、介護職員の負担軽減や効率化を推進するため、介護ロボットや先端機器などの導入を更に推進してまいります。
令和5年度の国民健康保険被保険者における特定健診受診率は35. 3パーセントで、県内平均の39.0パーセントを下回っております。受診率の向上を図るため、引き続き特定健診受診者に抽選で特産品を贈呈する「健康になっGOTOプロジェクト」を実施してまいります。特に40歳から59歳までの方については、60歳以上の方と比べて受診率が低いことから、当選枠を拡大し、受診意欲を高めてまいります。
また、20歳から39歳までの方については、医師会、医療機関のご協力により、令和7年度から医療機関で個別健診を受診できるようになりますので、将来の特定健診受診率の向上につなげてまいりたいと考えております。
重症化予防については、特定健診受診者のうち医療機関の受診が必要な方に対する受診勧奨や保健指導を実施するとともに、糖尿病性腎臓病で通院している重症化リスクの高い方に対しては、人工透析への移行を防止するため、医療機関と連携して保健指導を実施してまいります。
五島市における死因の第1位は「がん」であり、全体の27.4パー セントを占めております。このため、「がん」についての正しい知識を普及し、がん検診の受診率向上を図ってまいります。特に胃がん検診の受診率は、令和5年度3.3パーセントと他のがん検診と比べて低い状況にあるため、重点的に受診勧奨を行ってまいります。また、要精密検査となった方に対しては、積極的に医療機関の受診を勧めてまいります。併せて、医師会や医療機関と「精度が高く、安心して受診できる検診」を目指し、協議を重ねてまいります。
五島市の自殺死亡率は、国や県と比較して高い状況が続いています。
「第2次五島市自殺対策計画(いのちの充電プラン)」に基づき、特に自殺が多い高齢者、生活困窮者及び働き盛り世代への支援を重点施策として、関係機関と連携・協力を図りながら、自殺対策を推進してまいります。
令和6年度から、40歳から70歳までの5歳刻みの節目の女性を対象に骨粗鬆症の集団検診を実施しておりますが、対象者の受診機会を増やすため、令和7年度から医療機関のご協力により、個別検診を追加します。骨粗鬆症になると骨折しやすくなり、要介護状態となる可能性が高まるため、早期に発見し治療につながるよう受診率の向上に努めてまいります。
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種の実施や接種勧奨を引き続き行ってまいります。また、令和7年度から帯状疱疹が季節性インフルエンザと同じ予防接種法のB類疾病に位置付けられることから、新たに帯状疱疹の定期予防接種を実施してまいります。
カネミ油症については、全国油症治療研究班が実施した次世代調査の 進捗状況が1月24日に報告されました。この調査には、これまでに4 43人が参加し、うち219人が検診を受診しておりますが、報告では、先天性異常の口唇口蓋裂は発生率が高い傾向にあるとしつつ、「油症との因果関係に言及することは難しい」とされました。
今回の報告に期待しておりましたが、新たな進展が見られなかったことにつきましては、残念であります。
五島市としては、引き続き次世代調査に全面的に協力するとともに、
「カネミ油症被害者に対する支援行動計画」に基づき、被害者の健康状態の把握や相談支援体制の強化に取り組んでまいります。
生活困窮者対策については、生活困窮者の多様化する問題に迅速に対応するため、4月から社会福祉課内に相談窓口を設置します。相談窓口では、生活困窮者相談支援員に加え、就労支援員や生活保護のケースワーカーが同席し、それぞれの専門知識を活かした支援方法を提供することで、生活困窮から早期に脱却できるよう支援してまいります。
ひきこもりについては、その状態に至った背景や現在置かれている状況が当事者やそのご家族によって様々であります。また、長期のひきこもりによって80代の親と50代の子が社会から孤立する、いわゆる8 050問題についても、今後も高齢化が進む五島市にとって心配される課題です。
このため、関係機関と連携を図り、個々の当事者やそのご家族の状況に応じた寄り添う支援を推進してまいります。ひきこもりに関して、平日に相談することが難しいケースもありますので、引き続き土曜日・日曜日の無料相談会を実施してまいります。
令和6年12月末現在、市内の介護認定者のうち、認知症又は認知症の疑いがある方は約1,900人で、認定者の6割以上を占めております。
令和6年3月に策定した五島市認知症施策推進計画に基づき、認知症への理解の促進、認知症の方の意思決定支援と権利擁護体制の充実、認知症の予防などの施策に取り組み、認知症の方が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう引き続き支援してまいります。
高齢者の介護予防については、社会参加や健康維持に高い効果がある地域ミニ・デイサービスを推進するため、引き続きボランティアの育成・支援に努めてまいります。
また、高齢化率が高まるなか、高齢者の見守り体制など地域福祉の充実が求められますので、見守りネットワーク連絡協議会の連携強化に努めるとともに、住民主体の集いの場の充実に努めてまいります。
障がい者福祉については、障がい者支援の更なる充実を図るため、4月から社会福祉課内に障がい者基幹相談支援センターを設置します。このセンターは、障がい者やそのご家族が抱える様々な問題に対応し、日常生活や社会参加を支援する拠点となります。専門職員を配置し、相談対応や情報提供、各種サービスのコーディネートを行うことで、一人一人に適した支援を提供してまいります。また、関係機関との連携を強化し、障がい者が地域で安心して暮らせる環境づくりを推進してまいります。
【インフラの整備】
社会生活の基盤である道路・橋りょうなどについては、計画的に整備・維持管理を行い、長寿命化に取り組んでまいります。
公共交通については、令和4年3月に策定した五島市地域公共交通計画に基づき、国、県、交通事業者と連携しながら、効率的で利便性の高い公共交通ネットワークの構築に取り組んでおります。
本土と五島を結ぶ航路・航空路については、島民の往来や島外からの観光・ビジネス客の移動など、五島市の経済活動に直結し、地域の維持・活性化に必要不可欠な公共交通機関として、極めて重要な役割を担っております。コロナ禍で減少していた利用者も回復傾向にあり、特に航空路の利用者はコロナ禍前を超える水準で推移しておりますので、これからも安全で安定した運航に向けて、航路・航空路事業者などと連携してまいります。
また、福江空港の更なる利活用により地域経済の活性化を図るため、同空港に給油機能を導入して全国からのアクセスを可能にし、多くの観光客を迎えたいと考えております。県や関係機関とともに調整を進めてまいります。
離島間航路については、奈留島を経由し福江島と新上五島町を結ぶ五島旅客船所有の高速船「ニューたいよう」の新造船が、6月から就航する予定となっております。引き続き、国、県と連携しながら航路の維持と利便性の向上に努めてまいります。
陸上交通については、交通空白地帯となった地域への乗合タクシーや電話予約制乗合タクシー「チョイソコごとう」を導入しており、引き続き、路線バスなどとの融合による公共交通ネットワークの再編に取り組んでまいります。
また、自治体やNPO法人などが運行主体となって、一般ドライバー が有償で乗客を送迎する公共ライドシェアについては、交通事業者の手が届きにくい地域の有効な交通手段となり得ることから、導入に向けた検討を進めております。交通事業者や地域の皆様のご意見を伺いながら、まずは玉之浦地区での実証運行の実施に向け取り組んでまいります。
移動販売事業を行っている事業者に対しては、移動販売車両の購入費用や燃料費の支援を行い、買い物にお困りの地域の解消に努めてまいります。
市営住宅については、老朽化が著しい第1丸木住宅の建替えを計画し、令和6年度に設計業務を実施しました。住宅の規模は、現在の36戸か ら10戸に縮小する予定で、令和7年度に着工し、令和8年6月末の完成を目指してまいります。
適切な管理が行われていない空き家については、所有者に一義的な責任があることを前提としつつ、地域住民の住環境に悪影響を及ぼしている現状を踏まえ、地域全体の問題として対策を講じていく必要があります。
このため、令和6年に指定した空き家の活用や管理に積極的に取り組む空家等管理活用支援法人の活動を支援しながら、空き家の情報収集や困りごと相談会を連携して実施してまいります。
また、新たな取組として、相続放棄などにより所有者が存在しない危険な空き家については、国の社会資本整備総合交付金を活用し解体除却を進めてまいります。
海ごみ対策については、市民の皆様のボランティア活動によるご協力もいただき、令和5年度の海ごみの回収箇所は75箇所、回収量は29 8.35トンとなっております。引き続き、美しい海岸景観の保持、環境保全のため、漂着ごみの回収・処分を行うとともに、発生抑制のためのイベントを実施し、更なる意識啓発に努めてまいります。また、県が離島の高校生を韓国に派遣し、海ごみについて韓国の学生と意見交流を行う「日韓学生海ごみ事業」を計画しておりますので、五島市も協力してまいります。
消防団については、地域の実情に応じた組織の再編に取り組んでおり、現在の1本部30分団、1,071人を令和7年度から1本部28分団、 999人に見直したいと考えております。各種災害など有事の際に、市 民の皆様に安心・安全を与える組織体制の維持に努めてまいります。
防災対策については、平成25年度に導入した防災行政無線が更新時期を迎えていることから、令和7年度から8年度にかけて、福江、三井楽、岐宿、奈留、久賀島及び椛島地区の設備を更新してまいります。更新に当たっては、通信方式の変更により音質を向上させるとともに、屋外スピーカーの一部を高性能スピーカーに変更することで、聞こえにくさの解消を図ってまいります。
また、河川の氾濫による被害を最小限にとどめることを目的として作成している五島市洪水ハザードマップについては、県が新たに追加した洪水浸水想定区域を反映し、更新してまいります。
5月31日には、令和7年度長崎県総合防災訓練が五島市と新上五島町で開催されることとなっており、五島市では、避難所開設訓練の実施などが予定されております。こうした訓練をはじめ、自主防災組織や各地域における防災訓練・講話などを通じて、住民の防災意識の向上を図るとともに、防災機能を強化することで、災害に強いまちづくりを推進してまいります。
【ゼロカーボンシティの推進】
2050年までにCO2排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティの実現に向け、令和5年9月に五島市ゼロカーボンシティ計画を策定しました。令和6年9月には環境省の脱炭素先行地域に選定され、1月1 5日の選定証授与式では、浅尾環境大臣から選定証をいただきました。これを機に、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を加速させてまいります。
令和7年度は、地域で発電した再生可能エネルギーを効率的に利用し、電力系統の混雑を解消するとともに、地域経済の活性化に貢献する新し い仕組みの構築を目指してまいります。また、公共施設における電力を再生可能エネルギーに切り替えるとともに、公共施設を中心に蓄電池併設の自家消費型太陽光発電を設置し、更なる再生可能エネルギーの地産地消に取り組んでまいります。